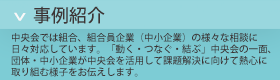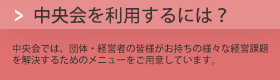テラコッタアートVASARA
IT活用で成功事例となり
伝統技術継承に尽くしたい
- 創立:
- 2008年
- 事業内容:
- 瓦・テラコッタ素材の
- 切り文字・小物・雑貨
- 製造・販売
- URL:
- http://www.vasara-sp.com/
- 中央会のアドバイスでネット販売を始めた
- 大会参加で実践的に分析・評価してもらえた
- 伝統を守り伝えるために情報発信を続けたい

瓦素材の切り文字「ナチュラル素材/島のめぐみ」
ネットショップオープン!
テラコッタアートVASARAは、粘土を箆(へら)で彫る「いぶし瓦」伝統の技法を用いて、独自の焼成方法で看板や表札(切り文字)など、新しい形の瓦を制作している。兵庫県中小企業団体中央会(中央会)との関わりについて、代表の清水氏に話を伺った。
清水氏は、「役物瓦」を作る瓦職人である「道具師」としての仕事の傍ら、瓦の可能性に挑戦すべく、展示会やイベントなどに出展し、新しい作品を発表し続けていた。所属する淡路瓦工業組合を通じ、中央会から「作品の性質上、インターネット販売に向いているのではないか?」とのアドバイスがあり、ネット販売を始めることに。それまでは組合経由でしか知らなかった中央会と、個人的なつながりができた。
特別賞を受賞

「行動したことに具体的なアドバイスをもらえた」と清水氏
ネットショップでは、店長としてブログを書いて情報発信していたが、次第に広がりがなくなり、行き詰まりを感じていた。巷ではSNSがあふれており、セミナーでfacebookの勉強をしたのをきっかけに自分でも始めてみることに。2013年の夏のことだった。
試行錯誤しながら続けていたが、1年ほど経っても手ごたえが感じられない。そんなときに中央会主催の「ITでプロモーション大会2014」開催を知り、参加を決めた。
「ITを活用して自社の魅力を伝える」という課題で、大会を前にセミナーが行われ、YouTube、facebook、Twitterなど、一通り学ぶことができた。氏は自分で撮影した動画をYouTubeにアップし、facebookで拡散するという作戦を立て、会期中に29本の動画をアップした。結果、特別賞を受賞した。
ひとりで続けていたときには、何が問題かが見えていなかった。大会に参加したことで、セミナーなどで一方的に知識を与えられるのではなく、行動したことに対して専門家から具体的なアドバイスをもらえたことが良かった。客観的な分析や指摘を受けることができて、頭の中で戦略が固まり、自分が今何をすべきかが見えてきたと言う。

中央会 谷﨑と
成功事例をつくりたい
職人として、技術の伝承に使命と責任を感じる。同時に、このままでは「ほんまもん」の技術を伝えきることができないという危機感も募らせている。瓦の需要は減り続け、閉じられる窯も多い。仕事が減っては若い後継者は望めない。だからこそ、自分が成功事例となって、後に続く人たちにバトンを渡したいと考えている。
工房から職人が直にものを売って成功している事例はまだまだ少ない。ネットで売れる、もうかるモデルケースになりたい。ITを活用して多くの人に関心を持ってもらい、利用してもらいたい。そうすれば、時間も資金もできる。後継者を呼び、技術を伝えることができる。
まずは情報発信を軌道に乗せ、次へのステップとしたい。中央会は個人でも話がしやすく、声をすぐに反映してもらえるフットワークの軽さがありがたい。今後も何かと相談したいと考えている。
担当者からひとこと
VASARAさんは淡路島の地場産業である「淡路瓦」を活かしたオシャレな小物、テラコッタアートを作られています。1点1点真心を込め焼き上げられたこの商品は、日本の歴史が詰まった瓦の新しい姿の一つとして、かわいらしさの中にも趣きが感じられる逸品です。瓦職人でもある代表の清水様は、商品のこだわりをお客様に伝えるために様々な活動をされています。日々勉強とおっしゃる姿には伝統品が生まれ変わるその原動力が感じられます!

担当者:谷﨑 友亜