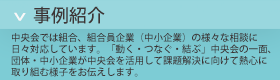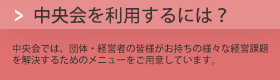株式会社青山産業研究所
日本伝統の留め具
こはぜを再認識して守り伝える
- 創立:
- 1919年(大正8年)
- 事業内容:
- 各種足袋用こはぜ・プレス部品・各種パッキン・座金等の製造・販売など
- 住所:
- 〒669-2202 兵庫県篠山市東吹366-1
- 連絡先:
- TEL:079-558-8418
FAX:050-3033-0452 - URL:
-
http://www.aoyama-kohaze.com/
http://kohaze.net/
- こはぜの新たな利用法、販路を模索
- 経営革新承認企業となり、様々な支援を活用
- こはぜを再認識、海外へ向けて発信中

代々受け継いだ手作りの こはぜ製造機
こはぜの可能性を探る
専用機械の製造業に発し、こはぜの機械の製造を請け負ったことから、こはぜの製造を始めることに至ったという株式会社青山産業研究所は、1919年創業。まもなく100周年を迎える。会長の青山氏の曽祖父である創業者が手作りしたこはぜ製造機が今も現役で動き続けている。
こはぜと言えば足袋、足袋と言えば着物…着物を着る機会が少なくなり、こはぜの需要も減り続けている。品質には自信と実績がある同社のこはぜだが、需要が着いてこない。優れた留め具としてのこはぜ、見た目にも美しい形状を持つ素材としてのこはぜを広めたい。ご夫婦でもある会長の青山氏と社長の久保氏は「あおやまこはぜ」として販路開拓に乗り出した。
道が開け始めた

左から社長の久保氏、会長の青山氏、中央会今橋
「あおやまこはぜ」として事業を展開するにあたり、銀行から「経営革新計画」の承認企業となることを勧められ、その支援機関として中央会を紹介された。申請書類の作成から承認に至るまで専門家の指導を受ける中で、中央会の今橋から国際フロンティアメッセへの出展を誘われる。
こはぜ以外にも弛まないナットという製品があり、そちらでは展示会経験があったが、こはぜでの出展は初めてのこと。今橋とはコンセプトづくりや展示のアイデア、POPに至るまで膝を詰めて話し合い、一緒に考えた。海外展開を見据え、KOHAZEと表記するアイデアも出してもらった。経営革新承認企業となったこともあり、ものづくり補助金や、小規模事業者持続化補助金もうまく利用することができた。展示会出展の反応は上々で、その後の努力の甲斐もあり、すでに衣類、雑貨、装身具、靴などコラボレーションから生まれた製品もでき始めている。
行動あるのみ!

和をアピールする展示会用ディスプレイ
海外展開を決めてからは、自ら積極的に海外へも出かける。JETROの海外ビジネス向けハンズオン支援も利用した。思いついたら全部調べる。問い合わせできる先には徹底的に相談する。アドバイスをもらったらまずはその通りに動いてみる…ご本人たちの努力あってのことだが、行動あるのみ!で活動していると、次々と道が開け協力者が現れるという。
パリでの展示会で出会ったドイツ人のクリエイティブディレクターは、こはぜに魅了され、海外展開についてのアドバイザーを買って出てくれた。ヨーロッパの人々は伝統を重んじる民族で歴史が大好きである点に着目し、日本人では当たり前すぎて気づかないような切り口でのアピール方法が提案された。こはぜ自体についても、ただの金具ではない機能的で美しい日本伝統の道具であること、そして、家族代々で守り継いできた素晴らしい技術の産物であることを強調するべきだと教えられた。
順調に進みつつある海外への展開に注力し続ける一方で、原点に返り足袋の良さをアピールしていきたいとも考えている。久保氏は最近足袋をはいての生活を始めたという。オーダーメイドで誂えた足袋の履き心地のよさを日々痛感しているそうだ。行動力で回りを巻き込み前進中のご夫婦は、これからも丹波篠山でひいおじいちゃんから受け継いだ機械を守り続ける。
担当者からひとこと
装飾品として生まれ変わった試作品を見るたびに、
一緒にワクワクさせていただいております。
何事にも真摯、そして全力で取り組まれるお姿が共感を呼び、
全くの新分野への進出であったにもかかわらず、多くの方の
支えをいただいて着実に前進されています。
今後の展開もとても楽しみです。

担当者:今橋 友亜